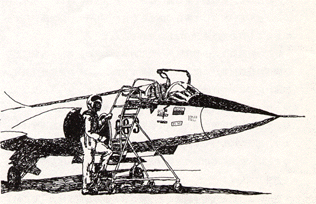
| 1 新戦闘機の必要性 |
| 2 機種内定の概要 |
| 3 機種内定後の動き |
1 わが国と海上交通 |
| 2 対潜水艦作戦と対潜機 |
| 3 次期対潜機装備の必要性 |
| 4 次期対潜機についての経緯と今後の方針 |
| 1 日米安全保障体制の意義 |
| 2 日米安全保障体制の信頼性の維持と円滑な運用態勢の整備 |
| 3 防衛協力小委員会の発足とその後の動き |
昭和51年12月9日,防衛庁は「新戦闘機の機種はF−15とし,52年度以降5個飛行隊分123機の整備に着手する」旨の方針を内定したが,51年12月21日の国防会議において「新戦闘機の整備に52年度から着手することは見送り,53年度には新機種の整備に着手することをめどに関係省庁で鋭意検討を進めることとする」旨が了承された。その結果,新戦闘機の昭和52年度整備着手は見送ることとなり,応急の措置として52年度予算においてF−4EJ12機の整備を行うこととなった。
現在,防衛庁としてほ昭和53年度から新戦闘機の整備に着手することをめどに,関係省庁と調整中である。
本節においては,「なぜ航空自衛隊が新戦闘機を必要とするか」,「なぜ早急に整備に着手しなければならないか」,「F−15を選定した経緯と理由はどうか」について言及し,最後に機種内定後問題となったことについて若干ふれてみることとする。
航空自衛隊が要撃戦闘機部隊10個飛行隊を保有する必要性については,既に第2章「防衛計画の大綱」において述べたところであるが,この10個飛行隊は,昭和52年度においてF−104J6個飛行隊及びF−4EJ4個飛行隊から成っており,今後,これら飛行隊の数は第17図のとおり推移するものと予測している。
すなわち,F−104J飛行隊は,昭和37年度から40年度にかけて編成されたものであるが,事故による損耗あるいは一定の飛行時間経過に伴う安全上の理由からの用途廃止によりF−104Jの機数は減少しつつあり,53年度には5個飛行隊となり,更に56年度からは毎年1個飛行隊づつ減少して,60年度には皆無となることが予測されている。
「防衛計画の大綱」に示されているとおり,航空自衛隊の主任務は,領空侵犯及び限定的かつ小規模の直接侵略に有効に対処することであり,その任務の円滑な遂行を図るためにも,減少するF−104J飛行隊を補充し,要撃戦闘機部隊10個飛行隊を維持しなければならない。
さて,減少する飛行隊を補充する際,考慮しなければならないのは,いかなる機種の戦闘機をもってそれを補充するかということである。
昭和53年度及び56年度におけるF−104J飛行隊の減少分については,F−4EJにより補充することとして,既に手当がなされているので,防衛庁としては,57年度以降の減少分について新戦闘機F−15により補充することを考えている。
昭和57年以降必要な新戦闘機をなぜ今から計画しなければならないかといえば,それは航空機の生産,飛行隊の建設などには少なくとも5か年という長い期間が必要であり,その必要な時期に間に合わせるためには,53年度から新戦闘機部隊の整備を開始しなければならないからである。
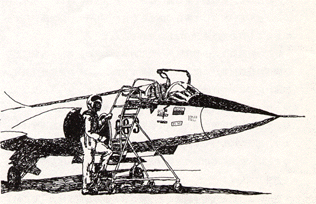 |
次に,なぜF−15という新鋭機をもって補充しなければならないのか,現有のF−4EJでは不具合なのかについて検討してみたい。
戦闘機の特徴として際立っているのは,その技術進歩が非常に早いことであり,また質の差を量で補うことが難しいことである。技術進歩がいかに早いかは,例えば小銃や大砲が中世以来数百年を経て今日の姿になっているのに対し,たかだか70数年前に初めて空中に浮かんだ航空機が,今や音速の何倍かということが問題とされる時代となっていることを見ても明らかであろう。また,質の差を量で補うことがいかに困難かは,例えば陸上戦闘の場合は,兵器の質の差を地形を利用したり,兵力を増加することによってある程度ほ補うことが可能であるが,防空作戦においては全天候能力を有する戦闘機に対して,その能力を有しない戦闘機は,雲の中での戦闘ではほとんど無力であり,また,優れた電子戦能力を有する戦闘機に対しては,この能力に劣る戦闘機の数を増やしたからといって,有効に対処することは困難である。これほど極端な差がない場合でも,その差を量で補い難いのが航空作戦の特徴であり,特に,ほとんど一瞬にして勝負が決まる今日の空中戦においては,わずかであっても質の差は決定的なものである。
最近の戦闘機は,小型軽量かつ大出力エンジンの開発,とう載機器及び機体の軽量化並びに機体強度の増強などにより,その運動性(上昇,加速,旋回などの性能)を飛躍的に向上させており,レーダー及び空対空ミサイルの性能向上ともあいまって,その攻撃能力を増大させている。また,航続距離の増大,航法装置の改善などにより,高入度はもとより,超低空においても広範囲に行動することが可能となっている。このことは,従来にも増して対戦闘機戦闘を重視しなければならないことを意味している。
更に,より精密な電子装置がとう載され,強力な電子妨害(ECM)を行うことが可能となり,また空対地ミサイルの小型軽量化により,戦闘機にもとう載できるようになるなど,多種多様な戦術戦法をとることが可能となりつつある。このような戦闘機の性能向上は,わが国周辺についてみても例外ではない。
航空自衛隊が現在保有するF−4EJは,今後とも比較的長期にわたり,わが国の主力戦闘機として防空任務に当たることとなるが,近年のめざましい航空技術の進歩に伴い諸外国に登場しつつある高性能の新鋭機あるいは新たに出現が予想される航空機と比較すると,いわゆる世代の古いものとなりつつあり,F−4EJでは,これら新鋭機に有効に対処しえない分野が多々生ずることが予測されている。すなわち,高性能の戦闘機及び戦闘爆撃機の出現並びに各種とう載機器の性能向上による侵攻様相の多様化に伴い,F−4EJでは高入度高速侵入目標及び超低空侵入目標に対する対処能力に限度があり,また対戦闘機戦闘や電子戦を行う場合にも能力上の格差があって,有効かつ効果的な防空戦闘を期待することは困難になると考えられている。
したがって,新戦闘機の整備に当たっては,5年先,10年先に予想される航空脅威に対し,質的能力の点で充分に対抗できる戦闘機が必要であると考え,以下述べるような長期にわたる慎重な調査と検討をかさねた結果,わが国の防衛上の要求に最も合致し,均衡のとれた戦闘機としてF−15を選定したものである。
わが国は,北は北海道から南は沖縄までの細長い島国であるという地理的な環境にあるので,防衛上の正面が広く,その天候,気象は変化に富んでいる。また,専守防衛を本旨としているので,航空作戦の主導権ほ侵攻する側にあり,航空自衛隊は常に受動的な作戦を実施しなければならない。これがため,新戦闘機は優れたレーダーとミサイルを持ち,天候気象のいかんや,昼夜を問わず要撃できる能力,すなわち全天候能力があること,侵攻機をレーダーで発見後できるだけ速やかに所要の空域に進出し,要撃態勢をとるため上昇性能,加速性能などに優れていることが必要である。
新戦闘機は,このような基本的に要求される能力のほかに,将来の航空技術の進歩に伴って可能であると予想されるさまざまなかたちの侵攻に対処できるものでなければならない。すなわち,高々度を高速で侵入する侵攻機,あるいはわが警戒管制レーダー網の盲点をついて低高度で侵入する侵攻機を機上レーダーで探知し,あらゆる方向からの要撃ができること,特に最短時間に要撃するため,侵攻機に対して前方から攻撃できる能力が必要である。
また,運動性の優れた戦闘機に対する戦闘能力や,電子妨害が種々なかたちで行われても,これを排除し,要撃することができる能力(ECCM能力),更に何等かの障害により,地上からの誘導が受けられない場合でも,独自に侵攻機を発見し要撃できる能力が必要である。そのほか,航空自衛隊の訓練環境,教育体系及び後方支援体系からみて受け入れやすいことも重要な要素であり,更には安全性が高く,整備しやすいことなどについても配慮されなければならない。
候補機種F−14,F−15,F−16の概要は,およそ次のとおりである。
F−14は,米海軍がF−4の後継機として採用した空母とう載用の戦闘機であり,制空,艦隊防空を主任務とし,対地攻撃任務を併せ持っている。本機は,主翼の後退角を速度及び高度に応じて変化させることができるほか,高性能の射撃管制装置及びフェニックスという優れた長射程空対空ミサイルを装備しているため,同時に多目標を攻撃できるという,他に類のない能力を持っている。
米海軍用に約520機,イラン向けに80機生産される予定であり,昭和52年3月までに約220機が部隊配備を完了している。エンタープライズ,ケネディ,アメリカ等の空母にとう載され,実戦配備についている。
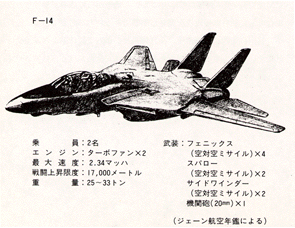 |
F−15は,米空軍がF−4の後継機として開発した戦闘機であり,制空戦闘を主任務とし,対地攻撃任務を併せ持っている。
本機は,機体重量に比して強力なエンジンを装備し,優れた運動性,巾の広い飛行領域,余裕のあるとう載能力などを有し,全天候能力,対戦闘機戦闘能力の面でも優れた戦闘機である。
米空軍用に約750機(試験用20機を含む),イスラエル向けに25機生産される予定であり,昭和52年3月までに約160機が部隊配備されている。
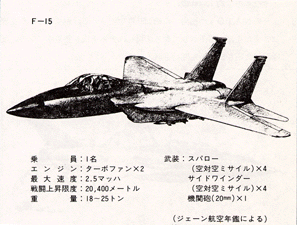 |
F−16は本来,新技術研究のための試験機として試作されたものであるが,その実用性が認められ,米空軍に採用された。米空軍では,軽量小型の戦闘機として,空対空任務においてはF−15と組み合せて補助的に使用されるほか,対地攻撃任務にも多用されるであろう。本機は,空気抵抗の減少を図ることなどのために翼胴結合部を一体化し,耐G座席を活用するなど,斬新な技術を多くとり入れると同時に,軽量,低価格を狙った戦闘機である。技術的には,空対空ミサイルのスパローをとう載し,全天候能力を付与することも可能である。
米空軍用に約1,400機,オランダ,ベルギー,デンマーク,ノルウェーのNATO4か国向けに約350機生産される計画である。量産機は,まだ生産に着手されておらず現在はテスト機を製造中である。部隊配備は昭和55年から開始される予定である。
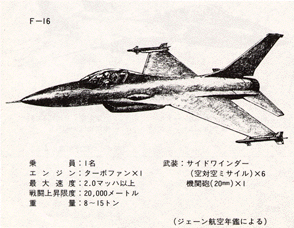 |
以上見たように,各候補機は,いずれも米海軍又は米空軍の使用目的に合うように設計されたものであり,それぞれ特徴のある優れた戦闘機である。しかし,わが国に最も適した機種は,わが国で使用する際の各種の条件に最も合致したものでなければならないので,米国における各機種の評価を防衛構想,地理的環境,運用条件等を異にするわが国にそのまま適用することはできない。かかる意味において,新戦闘機に期待する能力の面から,更にはわが国で使用する場合の防空効果などについても,各候補機の評価を行う必要がある。
そこでわが国の新戦闘機として期待すべき主な運用上の要求項目について,各候補機の能力を分析すれば次のとおりである。
全天候能力についてみれば,F−14及びF−15は,全天候下において運用するための十分な能力を有しているが,F−16が装備しているサイドワインダーは赤外線ホーミングミサイルであり,雲の中で使用できないため全天候下における戦闘能力には問題がある。F−16に全天候能力を付与するためにはレーダー誘導ミサイルのスパローを装備することが必要である。ただ,機体に比し大きなスパローをとう載することになれば,F−16本来の飛行性能を低下させることが危惧され,また機体が小型であるためレーダーの能力に物理的な限界が生じるおそれがある。
高々度を高速で侵入する目標に対処する能力については,F−14及びF−15はほぼ同程度であると思われるが,スパローをとう載した場合のF−16は,上昇性能,高々度飛行性能が低下するとともに,レーダーの探知能力が本来的に小さいこととあいまって,高々度高速目標に対処する能力は限定される。
前にも述べたように,航空技術,電子技術の進歩などに伴って,最近の新鋭機は警戒管制レーダー網の下をかいくぐり,超低空で海上又は地上すれすれに侵入して来ることが可能となっている。このような目標に,有効に対処するためには早期警戒機(AEW機)による警戒監視も必要であるが,戦闘機自体が低空の侵入機を捜索する能力,すなわち,海上又は地上からの反射電波の中から目標を区別するルックダウン能力をもっている必要がある。
各候補機はいずれも最新のレーダーを装備しているため,優れたルックダウン能力を持っているが,特にF−14及びF−15のレ−ダーは目標を遠方で探知できる能力を有している。
最近のめざましい航空技術の進歩によって,従来のように爆撃機のみではなく戦闘機,戦闘爆撃機でもわが国全土が行動範囲に入るようになっており,対戦闘機戦闘の行われる可能性は従来よりー層大きくなっている。更に,最近の戦闘機に共通する傾向としてみられるように,機体重量に比して,とう載エンジンの推力が増大した結果,上昇性能,加速性能,旋回性能などが向上しているので,対戦闘機戦闘能力,特に運動性を一層重視する必要がある。
各候補機は,いずれも優れた対戦闘機戦闘能力を有しているが,各種の実測データを分析した結果,運動性の点ではF−15に一日の長ありという結論をえた。
近代科学の粋を集めた電子機器を縦横に使う航空作戦においては,相手の航空機に目つぶしを加えたり,誤った判断をさせるための電子妨害が強力に行われる。
したがって,適切な要撃を行うためには,このような電子妨害を回避したり,見破って本当の目標を補捉する能力が是非とも必要である。このECCM能力については,F−14及びF−15はほぼ同程度の優れた能力を有している。
将来における航空作戦においては,地上からの誘導がないか又は不十分な場合にも,独力である程度の要撃戦闘のできる能力が要求されることになる。戦闘機が独立戦闘を行うためには,機上レーダーの捜索能力と敵味方識別装置の能力が決め手になるが,F−14及びF−15はほば同程度の能力を有している。F−16は,レーダーの探知能力が比較的小さいこと及び敵味方識別を自ら行う装置をとう載していないため,レーダーサイト又はAEW機からの情報がえられない場合は,F−14,F−15に比べどうしても格差が生じることとなる。
戦闘機としての性能が優れているというだけでは,わが国の要撃戦闘機として選定することはできないので,わが国の運用環境及び防空体系の中における各候補機の防空効果及び費用効率について,電子計算機を用いて模擬防空作戦を行うなど,科学的分析評価手法により総合的な評価を行った。
その結果,一定の防空効果を上げるために必要な戦闘機部隊の規模は,F−15の場合が最も少なくてすみ,また,一定の経費で整備しうる部隊規模により上げることができる防空効果もF−15が最も優れているとの結論に達した。
以上の分析をまとめれば,F−15はわが国の運用目的にも合致しており,将来予想される各種の航空侵攻,すなわち亜音速から超音速,低高度から高々度までの広い速度・高度領域にわたっての各種侵攻様相のもとにおいても,有効かつ適切に対処することができる能力を有する均衡のとれた優れた戦闘機であるといえる。
また,わが国の防空体系における防空効果及び費用効率の点でも,航空自衛隊が装備すべき新戦闘機としては,F−15が最適であると認められる。
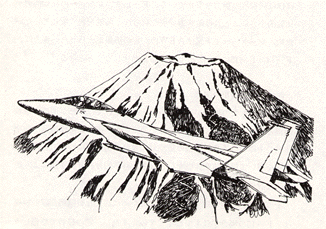 |
防衛庁は,昭和51年12月9日,新戦闘機の機種をF−15とし,52年度以降5個飛行隊分123機を整備することを内定しだが,51年12月21日に開催された国防会議において,次の趣旨のことが了承された。
「新戦闘機のような大型プロジェクトの決定には,関係省庁間の十分な調整,国防会議における慎重な審議が必要であるが,現在の状況にかんがみ,十分な調整,審議を行うだけの時間的余裕がないので,新戦闘機の整備に昭和52年度から着手することは見送り,53年度には新戦闘機の整備に着手することをめどに関係省庁で鋭意検討を進めることとする」これを受けて,防衛庁では新戦闘機の昭和52年度整備着手を見送り,応急の措置としてF−4EJ12機の追加調達を行うこととした。以上のようなことから,防衛庁では,所要機数については更に検討中であり,昭和53年度にはFー15で所要の予算措置が行われることをめどに,引き続き関係省庁との調整を行っているが,最近,F−15をめぐって次のような動きがみられる。
昭和52年2月24日の米国上院軍事委員会において,ブラウン国防長官は,キャノン民主党議員の質問に答え「F−15は全天候能力と格闘能力に優れた戦闘機である」旨前置きしながら,「F−15の武装すなわちスパロー(AIM−7F)ミサイルとその射撃管制装置は要求性能を満足せず,かつ,要求性能を満足するようなスパローミサイルは今後5年くらいの間にできるとは思われない」旨の証言を行った。この証言は,1978年度米国防予算案に関するカーター政権の改定提案に関連して行われた国防長官の数回にわたる証言の一部をなすものであるが,防衛庁が新戦闘機として内定したF−15には欠陥があるのではないかとの疑惑を生むこととなった。
防衛庁は,この報道に接し,直ちに外交ルートを通じて,この証言の内容及び真意について米国防省に照会するなど真相解明のための措置をとった。
その後3月14日,入手した米国防省の回答等によれば,
![]() F−15は極めて傑出した全天候制空戦闘機であり,今後長期にわたり第一線機として活躍するであろう。
F−15は極めて傑出した全天候制空戦闘機であり,今後長期にわたり第一線機として活躍するであろう。
![]() 射撃管制装置は設計仕様を満足しているので,これに大きな改修を実施する計画はない。また現在スパローやサイドワインダーミサイルについても発射上の問題は特にない。
射撃管制装置は設計仕様を満足しているので,これに大きな改修を実施する計画はない。また現在スパローやサイドワインダーミサイルについても発射上の問題は特にない。
![]() F−15の生産を従来の月産9機から6.5機に減らしたが,このことは米空軍の調達機数729機を削減するものではない。
F−15の生産を従来の月産9機から6.5機に減らしたが,このことは米空軍の調達機数729機を削減するものではない。
ことなどが明らかになった。
以上![]() ,
,![]() のことは,防衛庁が昨年実施した新戦闘機に関する調査結果とも一致しており,性能などについて特段の問題点は認められなかったことを意味している。
のことは,防衛庁が昨年実施した新戦闘機に関する調査結果とも一致しており,性能などについて特段の問題点は認められなかったことを意味している。
これらの内容などについては,3月30日付ブラウン国防長官から三原防衛庁長官に送られた書簡によっても確認されており,前述のブラウン国防長官の証言が引き起したF−15の性能面に関する誤解や不安は解消されたものと考えている。
昭和51年12月,機種内定時における防衛庁の見積りによれば,調達機数を123機とし,昭和52年度予算で29機調達する場合の航空機単価は平均約72億円と試算された。本来航空機の単価は,総生産機数や生産ペース(月当たりの生産機数),生産関連諸経費の変動(人件費,部品費等),調達時の経済変動(インフレーション,為替レート等),取得方式(輸入,ライセンスによる国内生産等)などいろいろな要因によって決まるものである。しかもF−15は米国製航空機であるから,日本国内の諸要因にとどまらず,国外,特に米国の影響も受けることとなる。上記72億円という単価は,これらの要因を十分に考慮し,最も経済的に取得することを前提として見積られたものである。
昭和53年度の予算要求のための見積価格もこのような考え方で算定されることになるが,現状から推量すれば,今後,価格に影響を及ぼす要素としては,調達時期における経済変動と米空軍向けFー15の生産ぺース削減の問題などが考えられる。このうち,経済の変動は予測が難しく,現在その影響を正確に見積ることは困難である。F−15の生産ぺースの削減の問題については,仮にこれが実現した場合,米空軍向けF−15の調達価格は若干上昇するものと予想され,輸入機や輸入部品などに対しては影響が出ることは避けられない。しかしながら,防衛庁が装備を予定しているF−15は,主としてライセンス国産により取得することを考えているので,国産分を含めたF−15全体の経費に大きな影響が出るとは考えていない。いずれにしても防衛庁としては,削減間題の帰すうを注視し,価格の問題についても,引き続き米側との文渉を続けるとともに,資料め収集にも努め,見積価格の適正を期したいと考えている。
海上自衛隊は,現在さしせまった重要な問題の一つとして,現有の対潜機に代わる次期対潜機の選定という問題に直面している。
本節においては,「なぜ対潜水艦作戦がわが国の防衛にとって重要なのか」,「なぜ次期対潜機が必要なのか」,「なぜ早急に選定する必要があるのか」等について説明し,更に現在までの選定の経緯や今後の方針についても付言することとする。
わが国は狭い国土に多くの人口をかかえ,資源のほとんどを海外に依存している先進工業国であり,わが国が生存と発展を続けるための選択としては,世界の国々との友好を基盤とした貿易立国しかありえない。
先年の石油危機を回想する時,石油の輸入量は実際にはほとんど減少していなかったにもかかわらず,これがいかにわが国の経済と社会を根底からゆさぶり,国民生活を不安と混乱におとし入れたかは,まだ記憶に新しい。
このように海外から何の不安もなく入ってくるものと思っている石油,鉄鉱石,食糧等をはじめ重要物資の輸入が,一時的にせよ途絶えることがあれば,いかに深刻な事態を招来するか,あの時の苦い体験からも容易に想像できよう。
わが国の総輸入量は,これらの重要な物資を中心として年間5億ないし6億トンにも及んでおり,石油,鉄鉱石,小麦等は消費量のほとんど100%を,石炭はその80%近くを輸入に依存している。そしてこの膨大な物資の輸入は,そのほとんどを船舶による海上輸送に頼っている。
今後ともわが国が生存し繁栄していくためには,重要物資の安定供給を図ることが必要不可欠の要件であることはいうまでもない。そのためには諸外国との友好を促進することにより,供給源を確保するとともに,わが国の生命線ともいうべき海上文通の安全を維持する努力が必要である。
それでは海上交通の安全を危うくするものは何であろうか。有事,海上交通を妨害したり,しゃ断するために使用される兵器としては,潜水艦,航空機,水上艦艇,機雷等があるが,それらの中でも最大の脅威となものは,海中深く潜航し,隠密裡に行動できる海の忍者ともいうべき潜水艦である。
近時,各国は潜水艦の性能向上に多大の努力を傾注しており,科学技術の進歩とあいまって,将来更に多数の高性能の潜水艦を保有することになろう。このことはわが国周辺諸国においても例外ではない。
わが国としては,海上交通の安全がわが国の生存と発展にとって不可欠である以上,その最大の脅威となる潜水艦に有効に対処しうる能力を高めるようなお一層努めなければならない。もちろん,広大な海洋における海上交通の安全をわが国のみで確保できるわけではなく,友好諸国の協力をうることが是非とも必要であり,そのためには,わが国自らも応分の努力をしなければならない。
また,このような努力はわが国の防衛の基調となっている日米安全保障体制の信頼性をより高めるきずなともなるものである。
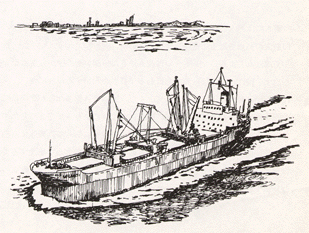 |
潜水艦は海水という天然の厚いべールの奥深く潜航することにより,その最大の利点である隠密性を保持している。
光線はもとより,レーダーの電波も通さない深い海の中から潜水艦を捜し出す手段は,もっぱら海中を伝わる「音」を利用する以外にない。一般に,海中は静かな世界と思われているが,実は種々雑多な音が充満しており,また音の伝わり方も,海域,季節,深度等によりさまざまに変化する特性を有している。このような複雑な海水の特性に加えて,後述する潜水艦の性能向上に伴い,海の中から潜水艦を捜し出し,これを撃沈することはますます困難となりつつあり,反面これを克服するためには,最新の科学技術と高度の技量を必要とするようになっている。
対潜水艦作戦(対潜戦)の流れを要約すると
という段階を経て,撃沈にいたる。
第18図に示すように,潜水艦を捜索し攻撃する手段として,航空機,水上艦艇,潜水艦等が用いられるが,水中に潜っている潜水艦を必ず撃沈しうるような単一の対潜兵器,単一の作戦は存在しない。また近い将来においても,まず出現するとは考えられない。このため,各国とも第4表に示すような各種の対潜兵器を有機的に組み合わせ,相互の短所を補い,各種の作戦の総合効果によって潜水艦に有効に対処しようとしている。
各種の対潜兵器の中で,特に対潜機は広範な海域を速やかに捜索するのに適しており,また遠くの洋上に概略の位置の情報をえている潜水艦に対し,迅速に進出し,捜索攻撃ができるという他のものでは果たしえない大きな能力を有しており,対潜戦を行う上に不可欠のものである。このため,諸外国においても,高性能の対潜機を装備することに多大の努力が払われている。
対潜機は,また単に対潜戦のみならず,哨戒や機雷敷設等に用いられるほか,そのすぐれた航続力や捜索能力等の特徴を生かして,平時から,次のような各種の重要な任務にあてられる。
侵略を未然に防止するためには,平時から国土の周辺における艦艇の動き,その他の情況を常続的に把握し,情勢の変化の徴候を発見して,的確な情勢判断に資することは極めて重要である。このような周辺の情況を把握するための警戒監視行動には,対潜機が最も適している。
更に,対潜機は海洋調査,流氷観測,漁業監視等にも適しており,また,外洋における遭難船舶等の捜索救助,患者輸送等の民生協力にも利用できる。
(注) 広域水中捜索 潜航中の潜水艦を捜し出すには,広い海域に,一定の間隔をおいて水中音波受信装置(ソノブイ)を投入し,これから送られる多種多様な海中雑音の中から潜水艦の徴候を示す音(エンジンや推進器が発生する音)を選別する。
(注) 目標識別 上記の音を更に分析検討し,潜水艦であるかどうかを判定する。
(注) 位置局限 広域水中捜索の時点では,潜水艦の存在範囲は概略しか判らないので,識別した潜水艦の音を追跡し,その範囲を縮小する。更に正確な位置を出すため,水中音波受信装置から音波を発射して,潜水艦からの反響音を測定し,位置を決定する(この方法は正確に探知できるが,探知距離は比較的短い)。また地磁気が潜水艦の存在により乱されるのを検知し,潜水艦の位置を決定する方法もある(探知距離は,音波を発射して反響音を測定する方法より更に短い)。
(注) 攻撃 対潜ホ−ミング魚雷を主用するが,他に対潜爆雷,対潜ロケットがある。
(注) 主要国の代表的な対潜機
P−3オライオン(米国,オーストラリア,ニュージランド,ノルウェー,スペイン,イラン)
ニムロッド(英国)
アトランティック(フランス,西独,イタリア,オランダ)
CP−140(カナダ)
IL−38(ソ連)
S−3A(米国)
近時,科学技術の進歩に伴い,各国における潜水艦の性能向上には著しいものがある。特に,原子カエンジンを装備した原子力潜水艦(原潜)は,ディーゼルエンジンを装備した在来型潜水艦(在来型)と比較して,その性能に格段の差がある。このため,世界の主要国は潜水艦の原子力化に努力しており,例えば米国及びソ連の原潜の増加は第19図に示すとおりであって,将来とも逐次増加していくものと見込まれている。
潜水艦の性能は,潜航持続力,速力,潜航深度及び静しゅく度によって評価することができる。
以下これらを評価尺度として,原潜と在来型の性能を比較してみる。
在来型は,海中ではディーゼルエンジンを運転することができず,もっぱら蓄電池を使って推進器を回し航走するため,蓄電池の性能は向上しているものの,一定時間潜航した後は蓄電池を充電するため,少なくともスノーケルを水面に出さなければならない。
一方,原潜はその動力源として,空気を必要としない原子力エンジンを運転するため,潜航持続力は無制限に近く,在来型が可潜艦(海中に潜没できる艦)であるのに対して,原潜は文字どおり真の潜水艦であるといえる。
近時,蓄電池の改良により,一時に大電力を発生することができるようになったため,在来型でも20ノット位の高速を出すことが可能になった。ただこのような高速を使用した場合,蓄電池が急速に放電してしまうため,その持続力は極めて短い。したがって,潜航時間を維持しようと思えば,当然,低速を使用せざるをえない。
一方,原潜ほ潜航時間の制約を受けず,連続して高速を出すことができる。現在の最高速力は30ノットを越えているが,将来はエンジン出力の増大により,更に高速のものが出現するものと予想される。
原潜と在来型で潜航深度に差はないが,両者とも船体の強度の向上に伴い,より深く潜航することが可能となっている。
在来型は,潜航中蓄電池によりモーターを回し推進するので,艦内動力源等の発生音は極めて低い。
一方,原潜は潜航中も原子カエンジンによりタービンを回転させて推進するので,艦内動力源等の発生音は在来型より高い。現在の原潜は,初期のものに比べはるかに静しゅくになったが,それでも在来型に比較すると発生音は大きい。
以上述べたとおり,世界の主要国における潜水艦の中に占める原潜の割合は増大し,原潜は在来型に比べはるかに優れた性能を保有しているが,全く弱点がないわけではない。それは発生音が比較的大きいということである。
したがって,対潜部隊としては,その発生音を探知のためにいかに利用するかということが原潜に対処する決め手であるといえよう。
先に述べたとおり,潜水艦の中に占める原潜の割合が増大していること及び在来型の性能も向上していることにかんがみ,対潜部隊に対しては,これらの潜水艦に有効に対処する能力の向上が要求される。
すなわち,対潜部隊は広い海域を,より速やかに,より密度の濃い捜索を行わなければならない。更にある目標の探知をえても,それが相手の潜水艦かどうかを迅速に識別し,攻撃できる範囲までに位置を局限し,潜航したまま高速で逃げまわる潜水艦を,的確に攻撃することができなければならない。このような対潜部隊にあって,重要な役割を果たす次期対潜機には次のような性能を具備することが要求される。
潜水艦の高性能化に伴い複雑化する対潜戦を迅速かつ的確に行うため,探知機器から送られる種々雑多な音を始め,電波,磁気等の多種多様な信号の分析識別及び目標の航跡,未来位置の予測,自機の位置の正確な計算,その他僚機等とのデータ交換等極めて多くの諸情報を短時間にかつ正確に処理できなければならない。このため,これらの諸作業をコンピューターを中心とする電子情報処理装置を活用して処理する必要がある。ちなみに,現有のP−2Jはこれらの処理をとう乗員の手作業に頼っており,そのため人間の計算能力の限界から,かなりの時間を必要とする上,場合によっては錯誤を生じるおそれもある。
現在,世界で使用されている近代化された対潜機は,処理能力の飛躍的な向上を図るためいずれも電子情報処理装置をとう載する傾向にある。
潜水艦の潜航持続力の増大,水中速力,潜航深度及び静しゅく性の向上に伴い,対潜戦を有効に実施するためには,複雑な特性を持つ海中を広範囲にわたって,長時間,精密に捜索しなければならない。
このため,広い海域に最適な間隔をもって投入された多数のソノブイから送られてくる信号を同時に受信し,その海域内に存在する雑音の中から,目標潜水艦の音紋を見つけ出すことのできる優れた探知機器をとう載する必要がある。
また,広い海域を同時に捜索でき,その海域に投入された多数のソノブイからの信号を同時に受信できるよう高い高度に滞空しうる能力も必要である。
また,投下されるソノブイ自体も,潜水艦のエンジンやスクリュー等から発生する音を,より遠距離から確実に捕えることができる高性能のものが必要である。
広域水中捜索においては,潜水艦の大まかな存在範囲は判断できるが,これを攻撃に結びつけるためには,更に精密かつ迅速に潜水艦の位置を局限する能力が要求される。
そのため,次期対潜機は高性能のソノブイや捜索機器をとう載でき,広域水中捜索を継続しながら,しかも簡単な手順で位置を局限しうる能力を持っていなければならない。
潜水艦の存在は自ら探知して知る場合もあるが,他からの情報をえて知る場合もある。
先に述べたように,潜水艦の水中速力及び潜航時間の増大に伴って,その潜在海域は時間の経過とともに一層拡大するので,ひとたび潜水艦の情報をえたならば,速やかにその海域に進出し,潜水艦を捜し出さなければ,攻撃に結びつけることができない。
このため,所要の海域に迅速に進出できる高速性と,更に航法援助装置に乏しい洋上において,自機の位置等を常に正確に知るための精密な航法能力等が必要である。
また,一般的に対潜機は,長時間行動するため,とう乗員の精神的,肉体的負担を軽減するよう配慮されていなければならない。
以上述べたところの次期対潜機に要求される性能を要約すると
・電子情報処理装置及び所要の捜索機器等をとう載すること
・高い高度における長時間の哨戒飛行が可能なこと
・進出速力が大きく,すぐれた洋上航法能力を備えること
・機内作業環境が良好であること
といえる。
現在,海上自衛隊の対潜機の主力として活躍中のP−2Jは,第2次大戦末期に原型が開発されたP2V−7の機体の長さを約1.3メ−トル延長し,軽量エンジンに換装することによって,とう載装備品を増大して対潜能力の向上を図ったものであるが,装備し始めてから,約10年を経過しており,次の点において旧式化している。
このため,情報処理に相当の時間を要し,高性能の潜水艦に対しては,時機を失したり,また錯誤を生じるおそれがあるので,有効な対潜戦を実施することが困難となってきている。
このように旧式化したP−2Jを更に改造し,対潜能力の向上を図ろうとしても,エンジン性能の向上,機体の改善等に限度があり,速力,航続距離及び高度に関する性能の大巾な改善は期待できない。
また,とう載機器についても,機体容積等に制約があるため,一部の機器の互換更新程度は期待できても,重要な電子情報処理装置,新型の水中捜索機器等は,とう載することが困難である。
P−2Jの対潜能力は,現状において,在来型に対してはー応の対処はできるが,原潜に対する能力は著しく低く,かつ,改造によってその能力の向上を期待することはできない。
ましてや,将来の時点において,在来型,原潜ともに,その性能が向上すること,また,原潜の占める割合が増大することを考えると,現有のP−2Jで対処することはますます困難になるであろう。
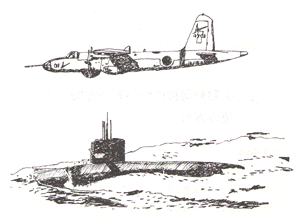 |
現在,海上自衛隊はP2V−7,S2F−l及びP−2Jの3機種,合わせて約120機の陸上固定翼対潜機を保有している。
このうちP2V−7は昭和56年頃に,S2F−1は58年頃に,それぞれ皆無となり,また現有の主力機であるP−2Jも,53年の約80機をピークとして逐次減少し,60年代後半には皆無になると見積られている。
このような陸上固定翼対潜機の減少を補い,「防衛計画の大綱」にいう,わが国周辺海域の監視哨戒及び海上護衛等の態勢を確保するためには,できるだけ早期に次期対潜機を選定する必要がある。
(注) ソノブイ 航空機から海面に投下する聴音ブイ。海中を伝播する音を捕らえ,このデータを電波で航空機に送信する。
(注) 音紋 潜水艦が発生する音を精密に分析した場合,指紋が、l人1人異なるのと同じように,潜水艦の型によってそれぞれ違った特徴を示す。
防衛庁は,昭和43年頃から対潜哨戒機能向上のため各種装備の部内研究を進めてきたが,列国潜水艦の性能向上に対応するためには,より性能の向上した新しい対潜機の開発が必要であるとして,45年度以降,毎年基本設計等のための予算を要求していた。
しかしながら財政上の理由もあり,政府全体としての結論がえられないまま推移していた。その後,昭和47年10月9日4次防主要項目決定に先立ち国防会議議員懇談会において,「次期対潜機の国産化問題は白紙とし,今後輸入を含め,この種の高度の技術的判断を要する問題については,国坊会議事務局に専門家の会議を設ける等により,慎重に検討する」旨の了解がなされ,この了解に基づいて48年8月10日国防会議事務局に「次期対潜機及び早期警戒機専門家会議」が設置された。
同会議は以後19回の専門家会議と7回の分科会を開催し,慎重な審議を行った結果,昭和49年12月27日に国防会議事務局長あて答申を提出した。その趣旨は「将来の装備化の時点において,国内開発のものをもって充てるか,外国機をもって充てるかについて検討したが,現段階でそのいずれかを否とする決定的要素は見いだせなかった」というものであり,「一般的には,事情が許すならば,国産化を図ることが望ましいといえようが,現実の問題としては,更に一段階先の研究開発を含みとしつつ,当面,外国機の導入を図ることも止むを得ない」との見解が付言されていた。
この答申は翌28日に開催された国防会議議員懇談会に報告されたが,同懇談会は,この答申の趣旨を参考にして,4次防における次期対潜機の国産化問題の取扱いについて,「その装備化を検討するに際し,必要となる技術的,財政的基盤等の諸条件につき,関係各省庁において速やかに調査検討すること」を了解した。
防衛庁はこの了解に基づき,国内開発あるいは外国機導入案のほか,機体は国内開発,とう載装備品は外国からの導入という折衷案についても調査検討を進めてきたが,最近米国においては,最新のとう載機器を装備した艦載対潜機Sー3Aが部隊配備され,カナダにおいても新しい対潜哨戒機CP−140の採用が決定される等の状況の変化が生じ,これらの調査検討も必要となってきた。
このため防衛庁としては,CP−140の細部内容について,昭和51年11月カナダへの海外調査を行い,一方S−3Aに関しては,来日した米国担当官より説明を受け,更にとう載機器等を機体と分離して導入し,これとわが国で開発する機体と統合する場合の技術的可能性,性能,経費等の細部を調査するため,52年2月米国ヘ技術グループを派遣した。
この次期対潜機問題については,昭和52年1月7日の国防会議において「引き続き検討を続け,できるだけ早期に結論を出す」という防衛庁長官の報告が了承されており,現在防衛庁においては,これまでに入手した各種資料をもとに前に述べた国内開条,外国機導入及び折衷案の各種のケースについて総合的に検討を進めている。
防衛庁としては,次期対潜機の選定については,いささかでも国民に疑惑を持たれるようなことがあってはならないので,慎重に取り扱う必要があり,純粋に防衛上の見地に立って所望の性能がえられ,費用対効果の優れたものを選定すべく,鋭意検討中であり,できるだけ早期に防衛庁としての結論を出したいと考えている。
1 昭和51年2月4日,米国の上院外交委員会多国籍企業小委員会の公聴会において,米国のロッキード社が,同社製のL−1011トライスタ−ジェット旅客機の日本等への売り込みに際し,多額の工作資金を贈った旨の証言が行われ,わが国に大きな衝撃を与え,更に,その後の証言で日本政府関係者もこれに関与していることが明らかとなるにつれ,大きな政治問題となるにいたった。
上記の証言は,民間旅客機の問題についてのみ言及されていたが,同社が対潜哨戒機(P−3C)を製造していたこと等から,防衛庁の次期対潜機の選定に関しても,この間の経緯に疑惑があるかのような報道がなされた。
2 ロッキード問題について国会で取り上げられた主な論点は,
![]() 防衛庁が昭和45年度から実施してきた調査研究は,国産を前提として進められていたものではないかということ
防衛庁が昭和45年度から実施してきた調査研究は,国産を前提として進められていたものではないかということ
![]() 昭和47年10月9日の国防会議議員懇談会において,次期対潜機の国産化問題が白紙とされたことをめぐって,これが既に国産の方針が決っていたものを事実上断念させ,輸入に導こうとしたものではないか,また,この白紙還元は特定の人によって決められたのではないかということであった。
昭和47年10月9日の国防会議議員懇談会において,次期対潜機の国産化問題が白紙とされたことをめぐって,これが既に国産の方針が決っていたものを事実上断念させ,輸入に導こうとしたものではないか,また,この白紙還元は特定の人によって決められたのではないかということであった。
しかしながら,それまでの間に,政府として次期対潜機の国産化が決定されたことはなく,開発のための予算も計上されていなかった。
また,国防会議議員懇談会の了解事項にある「白紙」の意味は「国産化を白紙とする」ものではなく,「国産化の是非に関する従来の議論を白紙とする」というものであり,この白紙還元は特定の人によって決められたものではなく,当日の議員懇談会における審議を経た上で決められたものであったことは明らかである。したがって,こうした疑惑はまったく根拠のないものであった。
なお,外国から装備品等を導入する場合,商社が介在することの得失の問題に関連した質疑も行われたが,防衛庁としては今回の問題を契機に,装備調達の一層の適正化を図っていく必要があると考えている。
昭和50年8月の三木首相とフォード大統領との会談と同月末の坂田防衛庁長官とシュレシンジャー米国防長官との会談の経緯にかんがみ,日米安全保障条約及びその関連取極の目的を効果的に達成するため,軍事面を含めて日米間の協力のあり方について研究,協議する必要が認められ,安全保障協議委員会の下部機構として防衛協力小委員会が設置された。
以下,日米安全保障体制の意義,防衛協力小委員会発足の背景,同小委員会の発足後の動き等について述べることとする。
今日の国際社会には,各種利害の衝突や対立が存続しており,また国際連合は,外部からの侵略を有効に阻止する機能を十分に果たすに至っていない現状にあり,地域的取極による集団安全保障体制により国の安全を保つことが依然として必要である。
わが国の防衛は,わが国自ら適切な規模の防衛力を保有し,これを最も効率的に運用しうる態勢を築くとともに,米国との安全保障体制の信頼性の維持及び円滑な運用態勢の整備を図ることにより,いかなる態様の侵攻にも対応しうる防衛体制を構成し,これによって侵略を未然に防止することを基本としている。
日米安全保障条約は,その第5条において,日米両国は日本国の施政の下にある領域における,いずれか一方に対する武力攻撃が,自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め,自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するよう行動する旨を規定している。
この体制によって,外部からのわが国に対する武力攻撃は,米国の強大な軍事力と直接対決する可能性を有することとなり,侵略国は相当の犠牲を覚悟しなければならないため,攻撃を蹄踏せざるをえない。
このように,日米安全保障体制がわが国に対する侵略の未然防止に果たす役割は極めて大きい。
万一,わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合は,日米安全保障条約に基づき,日米両国は各々の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するよう行動することとなる。
この場合における対処は,侵略の規模,態様等により異なるものであるが,武力攻撃を排除するため米軍と自衛隊が共同対処行動をとる場合においては,自衛隊は専守防衛の立場から主として防勢作戦にあたり,米軍には,日米安全保障条約に基づき自衛隊の行う作戦に対する支援等を期待することになる。
わが国は核の脅威に対しては,日米安全保障条約に基づき米国の核抑止力に依存している。
日米安全保障条約は,その第6条において,日本の安全に寄与し,並びに極東における国際の平和と安全の維持に寄与するため,米国が在日施設,区域を使用することを認めている。同条に基づき,米国はその軍隊をわが国に駐留させているが,この在日米軍のプレゼンスは,わが国の安全のみならず極東における国際の平和と安全の維持に貢献しているものである。
また,この条約は,軍事面の規定のほかに政治的,経済的協力関係の促進についても規定しており,このことは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」という名称にも現われているところである。
以上のとおり,日米安全保障条約を通じる日米両国の緊密な協調関係は,わが国の安全はもちろん,その発展と繁栄のために不可欠のものであるとともに,アジア・太平洋地域での安定した国際政治構造にとっても不可欠のものとなっている。
日米安全保障体制がいかなる時にも有効に機能するためには,日米両当事国の不断の努力が必要である。
日米安全保障体制の信頼性を維持し,その円滑な運用態勢の整備を図っていく上で,日米両国政府の関係者が日米安全保障条約及びその関連取極の運用について不断の協議を行い,お互いの意思の疎通を図っていくことは重要なことである。
これまで,通常の外交経路によるものは当然のこととして,総理訪米時における米国政府首脳との会談をはじめとする両国政府要人の間においても,安全保障問題につき意見交換が行われてきているが,主な協議の場としては,第5表にあげるようなものがある。これに加え,このたび日米安全保障条約に基づく軍事面を含めた日米間の協力のあり方についての具体的研究,協議を行うため,安全保障協議委員会の下部機構として防衛協力小委員会が設置された。
日米安全保障条約及び地位協定に基づき,米軍は,日本国の安全に寄与し,並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため,在日施設,区域の使用を認められている。この施設,区域をめぐっては各種の基地問題等が存在するが,わが国としては基地の整理統合をはじめとして,米軍基地の存在と地域社会の調和を図りつつ,米軍が在日施設,区域を円滑かつ安定的に使用できるよう,地位協定及び関係国内法令に従って所要の措置をとってゆかなければならない。
また,わが国としては,自らの問題として適切な規模の防衛力を保有し,これを最も効率的に運用しうる態勢を築かねばならないが,わが国がかかる努力を続けることは,日米安全保障体制の信頼性の向上にも貢献するものである。
このような見地からわが国としては,これまで第1次〜第4次防衛力整備計画を通じ,防衛力の整備に鋭意努力してきたところであり,今後も,新たに定められた「防衛計画の大綱」に基づき自らの防衛力を着実に整備し日米安全保障体制の充実に努めなければならない。
日米両国は,前に述べたとおり日米安全保障条約及びその関連取極の運用について,幾つかの協議の場を通じて種々の協議を行ってきたが,軍事面を含めた包括的な協力態勢に関する研究,協議は行われておらず,またそのための協議機関も設けられていなかった。
こうした状況を背景として昭和50年8月,三木首相とフォード大統領との会談が行われた際,日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用のために一層密接な協議を行うことが望ましいとの認識に至り,両国が協力してとるべき措置につき両国の関係当局者が安全保障協議委員会のわく内で協議を行うことが合意された。
また,これに引き続き行われた坂田防衛庁長官とシュレシンジャー米国防長官との会談において,有事の際,整合のとれた効果的な作戦行動を実施しうるよう日米防衛協力の諸問題について研究,協議するための場を設けることが合意された。
これを受けて,昭和51年7月開催された第16回安全保障協議委員会において,同委員会の下部機構として,防衛協力小委員会が設置されることが決定された。
防衛協力小委員会は,日米安全保障条約及びその関連取極の目的を効果的に達成するため,緊急時における自衛隊と米軍との間の整合のとれた共同対処行動を確保するためとるべき措置に関する指針を含め,日米安全保障条約に基づく日米間の協力のあり方に関して研究,協議を行うことを目的としている。
同小委員会は,日本側は外務省アメリカ局長,防衛庁防衛局長及び統合幕僚会議事務局長により,米国側は在日米大使館公使及び在日米軍参謀長により構成されるが,必要な場合は,適当な両国政府関係者の出席が認められている。
また,同小委員会が必要と認めるときは,その補助機関として部会を設置することができるとされている。
![]() 事前協議に関する諸問題,わが国の憲法上の制約に関する諸問題及び非核三原則は,研究,協議の対象としない。
事前協議に関する諸問題,わが国の憲法上の制約に関する諸問題及び非核三原則は,研究,協議の対象としない。
![]() 研究,協議の結論は,安全保障協議委員会に報告し,その取扱いは日米両国政府のそれぞれの判断に委ねられるものとする。この結論は,両国政府の立法,予算ないし行政上の措置を義務づけるものではない。
研究,協議の結論は,安全保障協議委員会に報告し,その取扱いは日米両国政府のそれぞれの判断に委ねられるものとする。この結論は,両国政府の立法,予算ないし行政上の措置を義務づけるものではない。
![]() わが国に直接武力攻撃がなされた場合,又はそのおそれのある
わが国に直接武力攻撃がなされた場合,又はそのおそれのある
場合の諸問題(基本構想及び機能調整に関する問題)
![]()
![]() 以外の極東における事態で,わが国の安全に重要な影響を与える場合の諸問題
以外の極東における事態で,わが国の安全に重要な影響を与える場合の諸問題
![]() その他(協同演習・訓練等)
その他(協同演習・訓練等)
の3項が了解されるとともに,当面![]() を中心に研究,協議を進めてゆくことが了解された。
を中心に研究,協議を進めてゆくことが了解された。
今後,同小委員会における活動を通じて,日米安全保障体制充実のために重要な日米間の協力のあり方についての研究,協議が着実に推進されることが期待される。